2018年5月29日
熱中症は例年7月、8月にかけて最も多く発生していますが、暑さに慣れていない時から注意が必要です。昨年は、5月、6月ともに熱中症で救急搬送された人数が全国で3,400人を超えました。早めに熱中症対策をはじめて、熱中症を予防しましょう。
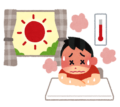
熱中症とは、暑い環境にいることで多量の発汗などにより、体内の水分と塩分のバランスが崩れ、体温などの調整ができなくなり発症する障害の総称です。
◆環境
○気温・湿度が高い
○風が弱い
○熱帯夜である
○扇風機、エアコンがない
○急に暑くなった
◆からだ
○高齢者、乳幼児、肥満
○糖尿病、心臓病などの持病
○下痢などの脱水状態
○寝不足などの体調不良
○二日酔い
◆行動
○激しい運動
○慣れない運動
○強度の作業
○長時間の屋外作業
○水分補給がしにくい
突然気温が上がった日や、急に蒸し暑くなった日にも体が暑さに慣れていないため注意が必要です。
熱中症は症状により下記のように3段階に分類されています。生命を守るためには、Ⅱ度(中等症)の段階で医療機関へ搬送することが必要です。
I度(軽症)
めまい、失神...立ちくらみ
筋肉痛、筋肉の硬直...
こむら返り
大量の発汗
II度(中等症)
頭痛、気分の不快、吐き気
嘔吐、倦怠感、虚脱感...
体がぐったりする、力が入らない、など。
III度(重症)
意識障害、痙攣、手足の運動障害...
呼びかけや刺激への反応がおかしい
ガクガクと引きつけがある。
高体温(38℃以上)...
体に触ると熱いという感触がある。
○気温が上がる前の対策
人が上手に発汗できるようになるには、暑さへの慣れが必要です。じっとしていれば、汗をかかないような季節から、ウォーキング等で汗をかく習慣を身につけて熱に慣れていれば、夏の暑さにも対抗しやすくなります。

○暑い日の対策

環境省では、環境省熱中症予防情報サイトで熱中症に関連する情報発信をしています。みなさんも参考にしてみてください。
参考:環境省 熱中症環境保健マニュアル2018
総務省消防庁 熱中症情報
(健康づくり推進部 菊池 香 2018.6)

新潟県労働衛生医学協会
(新潟ウェルネス)
編集部
健康診断・人間ドック・産業保健活動を通した健康づくり支援事業をもとに、皆様の健康意識を高めるためのお役立ち情報をお届けしています。
健康診断・人間ドック・産業保健活動を通した健康づくり支援事業をもとに、皆様の健康意識を高めるためのお役立ち情報をお届けしています。